毎月第一金曜日の夜、世界中のトレーダーが固唾をのんで見守る米雇用統計。前回は、この統計がなぜ為替市場に絶大な影響を与えるのかを解説しました。
今回は一歩踏み込んで、雇用統計の中でも特に注目される3つの重要項目に焦点を当てます。
- 非農業部門雇用者数(景気の「量」を測る)
- 失業率(労働市場の「割合」を測る)
- 平均時給(インフレの「質」を測る)
この3つの数字の意味と、それぞれがどう連動しているのかを理解すれば、より深く経済の動向を読み解くことができます。
① 非農業部門雇用者数:景気の勢いを測る「量」の指標
「非農業部門雇用者数(Non-farm Payrolls)」は、その名の通り、農業分野以外の産業で働いている人の数を示します。これがなぜ重要かというと、景気の拡大・後退を最もダイレクトに反映するからです。
- 結果が良い(予想より多い)場合
- 意味: 企業が積極的に人を雇っている → 経済活動が活発で景気が良い証拠。
- 市場の反応: 景気拡大 → 将来の金利上昇観測 → ドル買い(ドル高)
- 結果が悪い(予想より少ない)場合
- 意味: 企業が採用を控えている → 経済活動が停滞しており景気が悪いサイン。
- 市場の反応: 景気後退懸念 → 将来の金利低下観測 → ドル売り(ドル安)
この指標は、市場の予想と実際の数字がどれだけ乖離しているかが注目され、サプライズがあると為替レートが瞬時に大きく動く、最も注目度の高い項目です。
② 失業率:国民の仕事探し状況を示す「割合」の指標
「失業率」は、労働力人口(働く意欲のある人)のうち、職がなく求職活動をしている人の割合を示します。これは、個人の目線から見た景気や労働市場の需給バランスを測る指標です。
- 結果が良い(予想より低い)場合
- 意味: 仕事を見つけやすい状況 → 労働市場が引き締まっている(人手不足)。
- 市場の反応: 景気の安定・拡大と見なされ、ドル買い(ドル高)の要因に。
- 結果が悪い(予想より高い)場合
- 意味: 仕事を見つけにくい状況 → 労働市場が緩んでいる(人余り)。
- 市場の反応: 景気の先行き不安から、ドル売り(ドル安)の要因に。
失業率が低い状態は「完全雇用」と呼ばれ、経済が健全な証拠とされます。中央銀行も、この失業率の動向を金融政策を決定する上での重要な判断材料としています。
③ 平均時給:インフレ圧力を測る「質」の指標
「平均時給」は、労働者が1時間あたりに得ている賃金の平均額です。近年、この指標の重要性が非常に高まっています。なぜなら、物価の変動、つまりインフレの先行指標となるからです。
- 結果が良い(予想より高い伸び)場合
- 意味: 企業の賃金支払いが増加 → 人々の購買力が高まる → インフレ圧力が高まる。
- 市場の反応: インフレを抑制するため、中央銀行が利上げを急ぐとの観測が強まり、ドル買い(ドル高)に繋がりやすい。
- 結果が悪い(予想より低い伸び)場合
- 意味: 賃金の伸びが鈍化 → インフレ圧力が弱い → 利上げの必要性が薄れる。
- 市場の反応: 金利上昇期待が後退し、ドル売り(ドル安)に繋がりやすい。
たとえ雇用者数が増えても、平均時給が伸びなければ、力強い消費には繋がりにくいと考えられます。そのため、市場は「雇用の量」だけでなく「賃金の質」も厳しくチェックしているのです。
まとめ:3つの指標を組み合わせて読む
米雇用統計を分析する際は、これら3つの指標を総合的に見ることが重要です。
- 理想的な良い結果: 雇用者数↑、失業率↓、平均時給↑ → 素直にドル高
- 理想的な悪い結果: 雇用者数↓、失業率↑、平均時給↓ → 素直にドル安
- 判断が難しい結果: 雇用者数↑ だが 平均時給↓ → 強弱入り混じり、方向感が出にくい
このように、各指標が示すシグナルが一致しない「まだら模様」な結果になることも少なくありません。その場合、市場はどの材料をより重視するかを判断しようとするため、値動きが乱高下しやすくなります。
この3つの関係性を理解するだけで、経済ニュースのヘッドラインの裏側にあるストーリーが見えてくるはずです。ぜひ次回の米雇用統計から、この3つの数字に注目してみてください。


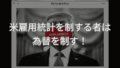
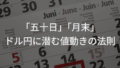
コメント